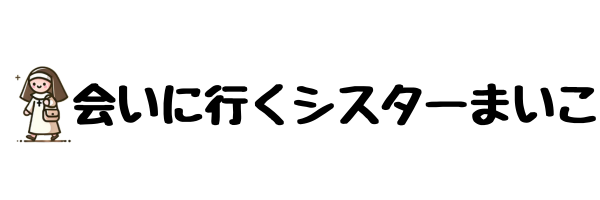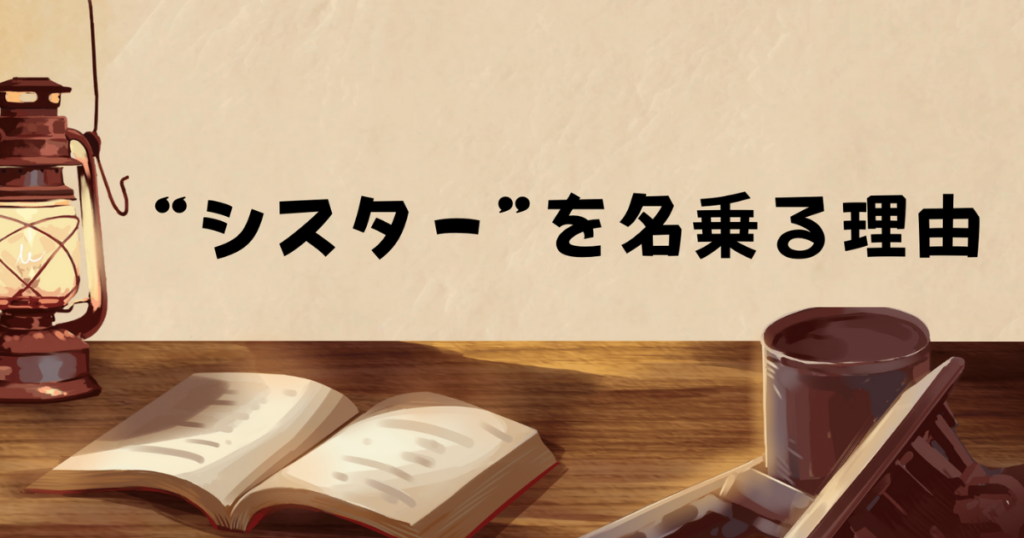
修道女ではないわたしがなぜ「シスター」と名乗るのか
「修道会に所属していないのに、シスターを名乗るなんておかしい」というお声をいただきました。
その気持ちは、分からなくもありません。
一般的に「シスター」と聞くと、多くの人はカトリックの修道女を思い浮かべるでしょう。
修道服を着て、誓願を立てて、修道会に所属している方々です。
でも、私はそうした制度には属していませんし、自分が修道女だと名乗ったこともありません。
それでも、わたしが「会いに行くシスター」と名乗ることには、確かな意味と根拠があります。
始まりは、ナイチンゲールと出会ったこと
わたしが「シスター」と名乗るきっかけになったのは、
ナイチンゲールの著作「カイゼルスウェルト学園に寄せて」を読んでいてのことでした。
彼女は、初代キリスト教から連綿と続く歴史の中で女性が担っていた
“ディーコネス”という存在に深い関心を寄せていました。
ディーコネスは、聖書のローマ人への手紙にも登場する、人々に仕える女性の奉仕的な役割のこと。
そしてナイチンゲールはこう記しています。
それは、誓約からも修道院の回廊付きの小部屋からも自由な形で存在した。
あまりにも多くの人々がこれをもっぱらローマ・カトリックから借りてきた制度だと思い、
そのために偏見を持っている。
私たちは様々な時代に、あらゆる教会の中で、そしてプロテスタント信仰のごく初期にも、
その聖務が存在していたことについて、他の多くの立証を示す余裕を持てたら良いのにと思う。
フローレンス・ナイチンゲール「カイゼルスウェルト学園に寄せて」より
つまり、人に仕える“シスター的な生き方”は、制度の中に閉じ込められるものではなく、
もっと自由で、愛に根ざしたものだったということです。
カイゼルヴェルトの「シスター」たち
ナイチンゲールが影響を受けたプロテスタントの牧師、フリートナーは、
ドイツで「カイゼルヴェルト・ディーコネス学園」を設立しました。
ここでは、女性たちが看護や保育などの奉仕を学び、卒業後は「シスター」と呼ばれました。
彼女たちは誓願を立てたわけではなく、修道会に属していたわけでもありません。
でも、“隣人に仕え、働く”というプロテスタント信仰の実践者として、
立派にその名にふさわしい歩みをしていたのです。
わたしにとっての「シスター」とは
だから、わたしが「会いに行くシスター」と名乗るのは、
制度や立場の問題ではなく、生き方としての“シスター”を選んだからです。
それは、誰かの上に立つ“支援者”ではなく、
ただ隣に寄り添う“隣人”として生きること。
形式や肩書きではなく、
確かな召命意識と、愛をもって生きること。
それが、私が“会いに行くシスター”と名乗る理由です。